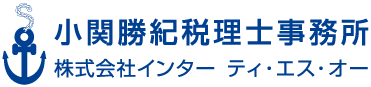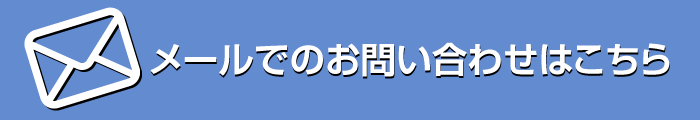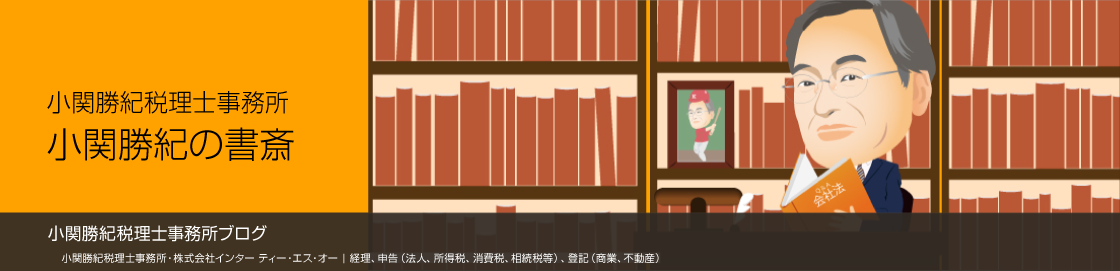伊能忠敬の格言の四選に
「歩け。歩け。続ける事の大切さ」
「一点に精神を集中すれば勉強や仕事に興味がわき、最上の結果にいたるでしょう」
「身の上の人は勿論、身の下にても、教訓異見あらば急度相用堅く守るべし」
「人間は夢を持ち、前に歩き続ける限り、余生はいらない」
座右の銘として「一身にして二生を経る」、また家訓として「正直・謙譲・実直」を掲げていたと言われ、肝に銘じたい言葉です。
伊能忠敬は、16年間で五千万歩を歩いたと言われたり、一日十里(約四十キロ)歩いたとも言われたりしていますが、一日一万歩を歩くだけでも大変なのです。
歩幅を正確に測るため一歩69㎝と決めて歩いたされています。
伊能忠敬は、天文学を高橋至時に学び、56歳から日本地図を作る第一歩を踏み出し、17年かけて日本全国の海岸線を歩き通して、精緻な日本地図を完成させたと言われています。
蝦夷地測量では我が町様似の海岸も測量で歩いたことでしょう。
天を測り、地を測った男が伊能忠敬です。
文政4年(1821年)伊能忠敬が亡くなって3年後、弟子たちによって「大日本沿海輿地全図」が完成された。
この地図がシーボルト事件となる。弟子に間宮林蔵がいます。
伊能忠敬(注1)は小関家の先祖でもあるので、東京都台東区の源空寺にお参り行きましたが、伊能忠敬と高橋至時の墓が並んで建てられています。
偶然にも、父の法名が「敬保」と「忠敬」の一字がありますが、その情報も知らせてないのに、お坊さんは「敬保」とつけ、忠敬の一字がある事に、後日になり気がつきました。
三百六十五歩のマーチの歌詞に「一日一歩三日で三歩、三歩進んで二歩さがる」ではなく「二歩進んで三歩下がる」とならないようにしましょう。
「千里の道も一歩より」で、前進あるのみです。
以前人間は直立二足歩行となったので発情期がなくなり、難産となったと書いたことがありますが、赤ん坊が生まれたらすぐ産声を上げるのは、難産で母親に自分の存在を知らせるためにとの事です。
歩くには、足ですが、足偏の漢字の一例に躓く(つまずく)、蹲る(うずくまる)、跪く(ひざまずく)、足りないとか否定的な意味が多いのは気になります。
「私の人生不足はない」と言ってみたいものです。
令和7年8月15日
小関勝紀
(注1)伊能忠敬の生誕
延亨2年1745年に現在の千葉県九十九里町旧(小関村)で生まれた。
小関五郎左衛門家の小関貞恒の第三子として生まれ幼名は小関三治郎といった。