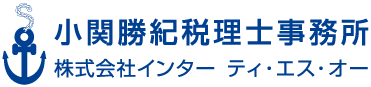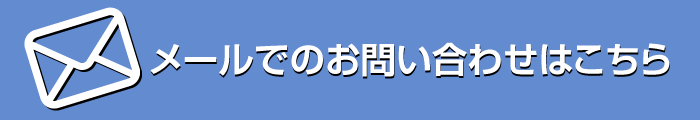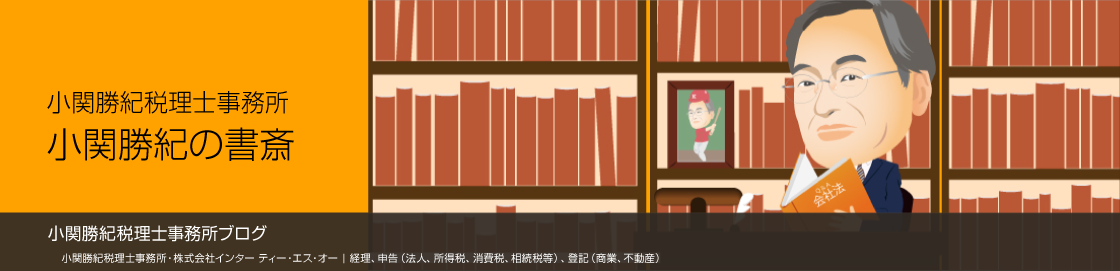先日の飲み会で、久しぶりの駄洒落を言う機会があり、以前見た張り紙に認知症にならないためには、「教育」とは、「今日行く」ところがある事、「教養」とは、「今日用」事がある事という張り紙の事を話したら一寸受けました。
「子ども食堂のための部屋」、「不登校のための部屋」として、安価で賃貸していますが、不登校の子供が日本では40万人いると言われている。不登校の理由は、色々な要素があります。
閉じこもりの大人も、相当の人がいるとも、言われています。
近年はインターネットの普及から、N高校、Z大学、放送大学と通信教育の普及は教育の機会を与えている事は称賛にあたえするすると感じています。
いつも見ているBSグリーンチャンネルの隣のチャンネルに放送大学のチャンネルがあり、何気なく見る機会があり、内容が素晴らしい講義内容なので感動しました。その講義内容は下記の(注1)テーマでした。
偏差値を上げるだけの教育は、学問ではなく、自然と接して、遊び、人間関係を経験しなければ、教育も教養も生かされないと、常日頃考えています。
ドイツの鉄血宰相のビスマルクの言葉で、「賢者は歴史に学ぶ」「愚者は経験に学ぶ」とあるが、まさにその通りです。
我々の士業(さむらいぎょう)も、国家試験として弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の資格取得で合格していても、業務、人間関係等の経験がなければ生業にはなりません。
勤勉意欲があれば、定時制、大学二部でも、夜に通える専門学校は沢山あり、特に都心では多くあります。
1582年の天正遣欧使節として、12歳くらいの少年たちの千々石ミゲル、伊東マンシュ、中浦ジュリアン、原マルチノの四人は、ポルトガル、ローマと見分した経験したことは、「百聞は一見に如かず」であったことでしょう。
また、1613年の伊達政宗の使節団の支倉常長(はせくらつねなが)「慶長遣欧使節」も、この時代には、カルチャーショツクは相当なものであったと推測されます。
804年代16次の遣唐使として最澄、弘法大使も唐の国をどのように感じた事でしょう。推測するに、海外の見聞はおそらく大変なカルチャーショツクがあったことと思われます。
10歳の昭和33年に私小関少年も、北海道から東京に蒸気機関車、青函連絡船で36時間での旅は、今77歳の喜寿になっても、見たもの聞くものは脳裏に焼き付いています。
「可愛い子には旅をさせよ」です。
教育の媒体がインターネットとなり、通信教育で十分と達成されます。ただ集団生活が不慣れとなり、人間関係がうまくいかない人が増加することには憂慮します。
日本の国民の三大義務(注2)の一つに「教育を受ける義務」があることから、義務教育には無償となっている。高校も無償化となる予定です。
2023年の私立大学等経常費補助金の交付状況は、交付学校数843校の交付総額は2976億であり、大学生一人の国家補助金は14万円くらいとある。
国がこのような厚い処遇をしても、当然の権利として感謝もしない輩が何と多いことか。
私が育った北海道では、日教組、北教組の組織にいる担任の先生含め学校のなかには、かなり存在していて、教壇に立っていながら授業しない先生、入学式・卒業式で「君が代」斉唱せず、天皇批判をする先生がいましたが、大人になった私からするとなんと幼稚な先生が多いことかと感じている昨今です。
認知症にならないためにも、今日行く(教育)とろろがあること、今日用事(教養)があることを実践して、大いなる好奇心と少々のお金を維持して、さらに国民の三大義務を実践して、 次の「米寿」を目指します。
(1注)その時の放送大学の講義内容
企業が直面する3種類の経営危機
- 突発的な環境変化による激しい危機
事故・事件や災害の発生による危機 - 急速な環境変化による重大な危機
COVID・19パンデミックによる経営環境の激変
リーマンショックの波及的影響
デジタル依存の急進およびサイバーセキュリティ問題の増大
地政学的事象によるエネルギー問題の深刻化 など - 継続的な環境変化によるゆるやかな危機
気候変動問題
リスクの種類
戦略リスク 組織目標が達成されないリスク
事業リスク 事業が失敗するリスク
オペレーションリスク 業務処理、業務運営が失敗するリスク
財務、財務報酬リスク 財政状況が悪化するリスク、財務数字を誤るリスク
ディスクロージャリスク 債務報告、リコール、不祥事などの情報開示が適切におこなわないリスク
市場リスク 為替レート、市場価格の変動によって損失を被るリスク
法的リスク 法規制などに反するリスク
ITリスク システム開発の目的が達成されないリスク
システム障害などのリスク(ITガバナンス確立できないリスク)
災害リスク 自然災害(地震・風水害など)と人的災害(犯罪・テロなど)のリスク
不正リスク 会社資産の横領や詐欺などの不正により損害を被るリスク
経営学におけるレジリエンス研究の必要性
近年では水や食糧をめぐる危機、サイバー犯罪、金融危機、地震や異常気象などの有事
事象が増大し、企業はこれら逆境への対処をもとめられている
レジリエンスとは、このような環境下で、ショツクや逆境を吸収し、対応し、回復する
力、および回復するシステムを作り上げることでビジネスがレジリエンスであればこそ
社会もレジリエンスとなります。
経営学におけるレジリエンス研究
組織的側面からのレジリエンス研究
マネジメント側面からのレジリエンス研究
レジリエンス(Resillence) 回復力・復元力
企業レジリエンスの要素
- 備えの段階での経験の蓄積
- リーダーの資質
- 自ら挑戦すること
- 組織外部のステークホルダーの存在
ビジネス・レジリエンス・マネジメント・フロセス
第一段階 レジリエンス土壌の分析
- 経営者の復元にかける気概・思い
- 経営者の現実的な楽観性
- 経営者の社員への気遣い
- 経営者の精神的・倫理観
- 自利よりも利他
- 企業ビジョンや企業使命の再確認
第二段階 レジリエンス力の評価 - 世の中に役立つ自社の商品・サービス
- 企業ビジョンと商品・サービス内容そして個人のビジョンとの連動
- 企業ビジョンと合致する人材の採用
- 会社の強みの理解と共有
- リスクを想定した会社のリソースと耐性
第三段階 レジリエンス手段の実行 - 経営者の率先垂範とリフレーミング
- ソーシャルサポート力、ネットワーク力
- 社員への自由と責任の付与
- リスクを想定した代替的なチャネル、ネットワークと柔軟性
- リスクマネジメント手段の効果的な組み合わせ
第四段階 レジリエンス情報の共有 - 企業ビジョン・強みの情報共有
- 社員の成長のための研修、情報共有
- 地域の人との情報共有
- ソーシャルリスクの情報共有と貢献
- 同業他社とのリスク情報の共有
(注2)国民の三大義務
- 憲法26条2項 教育の義務
- 憲法27条1項 勤労の義務
- 憲法30条 納税の義務
令和7年5月31日
小関勝紀