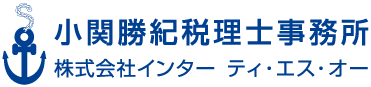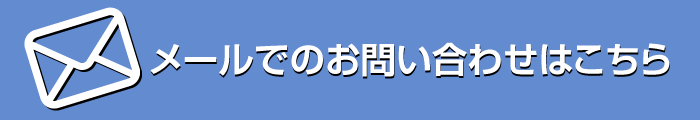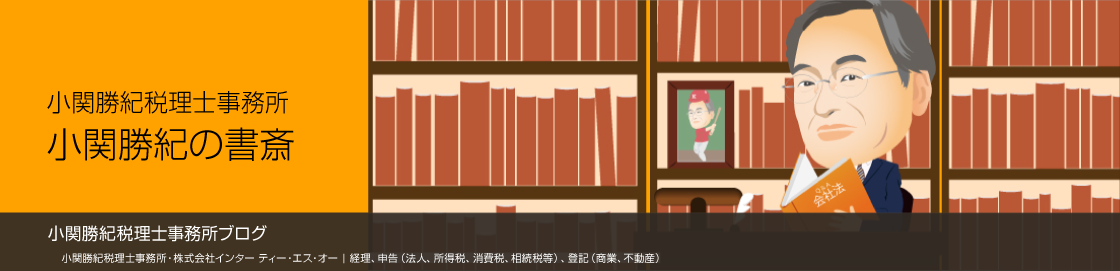北海道立様似高校時代の2、3生当時の担任であったS先生が亡くなったと、同級生のO君から連絡があったが、札幌の葬儀には、どうしても都合がつかず、生花の手配だけで、冥福を祈ることとなりました。葬儀に参列した、同級生たちの写真をラインで見ることとなり、時の経過を感じました。
今回のS先生の訃報で、この担任S先生から、高校三年二月初旬に「単位足りない。すぐ帰れ」と大学受験で東京に来ている時に、電報があったことは、自分のこれまでの人生、偶然な縁を思い出し考えさせられました。また、この電報が来たので想像もつかない、今の生業となっているのかなとも感じました。この電報がなければ、今はどうしているのか?
昭和39年の東京オリンピックも、舟木一夫の「高校三年生」という歌が大流行したときは、私は高校二年生でした。当時、私の実家は東京・練馬区にあり高校時代は下宿して様似高校に在学していました。
昭和41年2月に大学受験で東京に来ていた時に、担任のS先生から「単位が足りない。すぐ帰れ」という内容の電報が送られてきたので、受験途中で高校に帰ることとなった。
「化学」の卒業試験を受けてないで、東京に来ていたので単位をもらえず、単位不足で卒業できないということになるので、致し方なく帰りました。結局、化学のY先生からはレポート提出で単位をもらい、様似高校は卒業できました。今の時代では電報で連絡くるなどは想像つかない事です。
東京に来るといっても、当時は様似駅から東京・上野までは、電車、津軽海峡の連絡船と乗り換え36時間はかかる時代です。旅路は下記※いざ東京。
その時、東京経済大学の合格は決まって、様似に帰っていたので、この東京経済大学に入学することとなり、現在の生業となっています。自分の人生でこの「単位足りない。すぐ帰れ」の電報が無ければ違う人生を歩んでいたのかなと、感じています。
東京経済大学では、井尻正二さんのゼミに入ることとなり、考古学、地質学、古生物学となり、人体解剖、発掘と経験することとなりました。
井尻正二さんは、白菊会に登録していたので、献体して今は鶴見大学で骸骨となっているので、地上には存在しています。偲ぶ会が、没後3年間つづいたが、たまたま隣の席の人が小樽美術館のTさんでしたので、相続税の仕事をしたなかで、小樽出身の画家でYさんの絵画を小樽に返したいという相談を受けていたので、相談したら地元出身の有名な画家の若い時描いた絵画で、すぐ引き取りたいという事となりました。
この人体解剖の経験が唯物論の思想から、人間は死んだら「物」なんだから、精一杯生きろということを学んだような気がします。
大学院は法学研究科で当時、商法の合併をテーマにしていたのでしたが、これまた様似町に親戚がいるという、民法の品川孝二が指導教授となる事となり、テーマを借地権、地上権と変えることとなり二転三転することとなりました。品川孝二先生とは個人的なお付き合いで、何人か大学院の入学を縁故で許可してもらったこともありました。
法学研究科という大学院で、法社会学で有名な渡辺洋三さんが、私の研究室に訪ねてきて、君は井尻正二さんのお弟子さんか、言われたので改めて井尻正二さんの偉大さを知ることとなりました。井尻正二さんと渡辺洋三さんとは学士院会員で親交があったとのことでした。
学務課の窓口でまたまた卒業単位に1単位が足りないとやり取りをしていた現場に渡辺洋三さんが通り、話の内容から、俺の単位プラス1にしてやれと、学務課の人に話したりするくらいのいい時代です。渡辺洋三さんには、銀座に飲みに連れていってい個人的にはお世話になりました。
実際は学務課の担当者の計算ミスで今回は「単位」は足りていました。
この度、顧問先の訴訟事件で裁判所の証人として立ち会うこととなった案件で、その案件のU弁護士が北海道大学山岳部のOBで、井尻正二の地学団体研究会とは日高山脈を登頂する拠点が十勝広尾の坂本家(坂本直行)であつたと知っていたのですが、その坂本家の息子さんが偶然にも顧問先でもあったり、また訃報の連絡をくれたO君とはU弁護士とは北海道大学の勉強仲間であったと偶然な縁ばかりでした。
あの電報が来なければ、東京経済大学に入学することもなく、今どこで何をしていることか。多分何らかの生業をもって北海道で生活していたと思われます。
「善は急げ」でなく、「電(報)」は急げ」ですかね。
令和7年6月30日
小関勝紀
※いざ東京
始発駅様似駅を朝5時頃の始発列車に乗り、苫小牧駅で乗り換え函館駅に向かい、函館駅到着後は青函連絡船に乗り換え、青森駅から電車に乗り換え東京上野駅に向かい夕方5時頃の到着まで36時間を要する旅でした。青函連絡船に乗船するのは、乗船名簿を提出して、出航するたびに「蛍の光」が流れ、「銅鑼(ドラ)」が打たれ、紙テープで見送られ、船室は三等室での雑魚寝で、青森駅到着後は、予約席がないため列車の席を確保するため、駆け出さなければなりません。駅弁を何回か食べ、持参のスルメをかじりながらの旅を何回したことか。